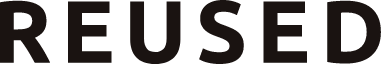編集長が大学院の講義のレポートとして書いた内容を掲載させていただきます。
示唆の得られるものになっているのではないかと。
【問い】
配偶者と同居する高齢者(男性)にとって「働く」とは?
【背景】
日本の生産労働人口は減少傾向(1)にあり、その中で一定の労働力を確保することを考えた場合に、高齢者の活躍は必須であり、「一億総活躍社会(2)」を実現するうえでも不可欠であると考えており、高齢者の就労人口(3)は毎年伸びている。
これまで、高齢者にとっての働くことの意味について断片的には触れてきたが、
一度、様々な角度から検討をおこなったうえで全体像を明らかにするためテーマとした。
なお、高齢者世帯においてもっとも多い「夫婦のみ世帯」(4)の男性の就労、を前提とさせていただく。
【枠組み】
本論は下記の枠組みで論ずることとする。
【本論】
- 本人について
・生きがいや社会的役割の維持(自己実現、社会とのつながり)
引退して社会とのつながりがなくなり孤立、孤独になることは認知症、抑うつなどに陥るリスクもあり、抑うつは精神的フレイルを引き起こすおそれもある。就業し続けることで生きがいを感じる(5)と同時に家庭内における役割の維持も図られる。配偶者(女性)は夫が仕事に出ている期間で自分なりの世界を家庭内でつくっており、夫が引退することで、その世界を邪魔されることを嫌うということもあり就業は夫婦円満にもつながる可能性がある。
また、仕事を通じた自己成長への意欲(6)はサクセスフル・エイジングを実現する上でも重要である。誰かの役に立っているという実感が老年期の課題へのよりよい対処につながる。
・経済的自立・収入の確保
現在においても、高齢就労者の就業の最大の理由は経済的理由となっており、公的年金に加えて労働による収入を得ることで、家計が安定する。公的年金の支給開始年齢についてはさらに引き上げられる可能性もある。(7)
・心身の健康維持(活動的な生活が健康寿命延伸に寄与)
フレイルのきっかけとしては、ソーシャルフレイル、つまりは社会とのつながりが減ずることでその兆候が現れる(8)とも言われている。働き続けることで社会とのつながりを維持し続けることはフレイル予防にもつながる。また、都市部においてはラッシュアワーを避けるなど通勤時間の調整は必要かもしれないが、通勤時の歩行などの適度な運動がADLの維持につながることもあろう。介護による経済損失は9.1兆円にものぼる(9)と経済産業省が発表している。
・体力・健康面での負担やリスク
年を重ねることで、視力、聴力など身体の機能は確実に落ちていく。若い時と同じ働き方は難しく、気持ちは働きたくても身体がついていかない恐れはある。暗順応、明順応などの働きにも衰えが出るため、明るいところから急にくらいところに入る、暗いところから明るいところに出るような就業環境は極力避けたいところ。補聴器をしていれば問題ないが、補聴器をしていない場合、自分宛ての連絡に気づかないなどのケースも考えうる。例えば腰痛などのように元々も持っていた持病がデスクワークなどを行った場合に悪化するおそれもある。
・新しい技術や業務への適応困難
流動性知能が加齢とともに低下するため、高齢者は新しい情報の獲得、や素早い適応力などに欠ける。変化が早く大きい現代のビジネスシーンにおいて、適応に苦戦する恐れがある。
一方で結晶性知能は年を重ねても一定レベルで維持される(10)と言われており、結晶性知能を活かせるジョブ・クラフティングが求められる。職業能力全般については業種ごとに変化の幅が異なるため、どのような業種かを加味して検討すべきである。
・エイジズムの影響によるストレスや孤立
年を重ねることで感覚能力、記憶力、情報処理能力は低下していく、そこで失敗を重ねると無力感を感じ抑うつ状態になる恐れがある。かつての部下が上司になり、指示をする側からされる側になること、エイジズムの標的になることも考えられる。本来、就業は社会とのつながりの維持による孤立・孤独対策になるはずが、孤立そして孤独に陥る(11)リスクがある。サクセスフル・エイジングにおいては、前向きさも重要な要素であり、前向きに環境の変化に適応する必要がある。
- 家族について
・経済的負担の軽減
年金以外の収入源が生まれ、年金のみでの生活に比べて家計が楽になる。(12)所属する会社の福利厚生にとっては、純粋なる給料だけではない恩恵を受けることもある。(昼食支給など)また、就業を通じて健康を維持することができれば、医療費の圧縮にもつながる。
・高齢者本人のQOLの向上による間接的なQOLの向上
高齢就労者が社会とのつながり、生きがいを維持することはQOLの向上、健康寿命の延伸にもつながる。それは間接的に家族のQOLの向上にもつながる(介護などのケアが必要な可能性が下がる)
・介護・家事負担の偏重による摩擦
事前に家庭内における役割分担に関する合意形成がなされていない場合、家庭内における家事(食事づくり、掃除、洗濯など)の負担にも偏りが生まれ不満が生じる恐れがある。家族介護が必要になった場合に、配偶者が就業を継続すると、介護を手伝ってもらえる機会も多くはなく、介護の負担に偏りが出る恐れはある。介護は精神的にも負担が大きく、介護にあたる家族に対してのケアが必須となる。(13)
- 企業について
・人手不足の解消
日本において生産労働人口は年々減少している。例えば、宿泊業などの一部の業種では人手不足により100%の稼働が難しいなどの状況を引き起こしており、労働力の確保は国内企業における重要事項の一つである。高齢者の雇用に際しては国からの助成金なども利用できる。(14)
・経験や知識、人脈の活用(若手社員の育成にも貢献)
コロナ禍あたりで、顧問派遣サービス(15)が流行っていた。端的に言うと、スキル・人脈を提供してもらい対価を提供するというもの。高齢就業者は長い社会人経験の中で身につけたスキルや豊富な人脈を有している場合もあり、それらのアセットを活用することで事業運営にプラスの効果をもたらす可能性がある。知恵などもスキルの1種であるということができる。
また、高齢者は高い感情的Well-beingを維持しているとも言われ、職場の雰囲気づくりにも寄与することも考えられる。
・多様な働き方推進による企業イメージ向上
多様性が世の中において重視される中で、企業のCSRという観点やSDGsの観点にも高齢者の就業は適っており、あらゆる人に優しい企業などのブランディングにもつながる可能性がある。
・体力・健康面への配慮や業務調整、賃金体型の見直しが必要
若手などに比べると、高齢就業者は身体機能や記憶力、注意機能などにおいて低下がみられるので、高齢者に合わせた業務設計が求められる。効率という意味での生産性を重視する業務などは向かない。ICTの効果的な活用により、誰でも一定のレベルで業務を遂行できる環境づくりが好ましい。賃金体型についても高齢者の就業を増やす前に見直す必要がある。(16)
・IT化や新技術への適応の遅れ
高齢者は流動性知能の低下により、新しい情報を取り入れることが苦手なため、デジタル人材育成の研修などを準備する必要も生じる。また、慣れるまでにも若者に比べると時間を有することもあり辛抱強く向き合うことが求められる。社内のDXを進めて、高齢者であっても自然にITを使いこなせるようにするなど、環境への工夫を施すという方法もある。スキル習得の観点なども含めて、リバースメンタリング(17)の仕組みづくりも有用と考える。
・若手社員の活躍機会の減少や人間関係の調整が必要
高齢就業者は疲れやすく、回復力も低下するので若者のようにフルタイムでの勤務が難しいことも起こり得るため、2人で1人区分の仕事をやってもらうなど、組織づくりにおいて調整が必要になる。また、任せる仕事の内容によっては若者に従来やってもらっていた仕事を高齢者にやってもらうなどのケースも考えられ、それを快く思わない若者がいると、若者と高齢者の間でコンフリクトが生じうる。
- 社会について
・社会保障負担の軽減(年金・医療費の抑制)
社会保障費は年々増加傾向にあり、令和3年には138兆7,433億円となり過去最高の水準(18)となった。高齢者の就労が健康寿命の延伸や年金受給時期の後ろ倒しなどにつながると社会保障費負担の軽減にもつながる。(19)
・多世代交流の促進による持続可能な社会の実現
家族の在り方も多様化する中で、様々な年代が職場で共に働くことで社会全体においてのエイジズムが弱まり、お互いに思いやりをもった共生社会の実現につながる可能性がある。高齢者の知識や経験が伝承されることも価値となる。
・これから高齢化を迎える外国へのナレッジの提供
ASEAN諸国なども経済の発展とともに高齢化が日本を上回る速度で進んでいく(20)とみられており、先に高齢化社会に突入している日本における成功事例やナレッジを提供し、ASEAN諸国のWell-being向上に寄与できる可能性がある。
・社会制度やインフラの更新・適応が必要
年金受給年齢や介護の社会化における制度の再考(一例として現金給付(21)を行うか)など、本人だけではなく、高齢就労者が社会で増えた場合にどのような変化が生じるかについて熟考したうえで、制度を見直す必要がある。例えば、高齢就労者が増えるにあたり企業において建物のリフォームが必要となった場合、その費用負担を企業だけに求めるのか、等もそれにあたる。
ここまで、本人、家族、企業、社会、の観点から「配偶者と同居する高齢者(男性)にとって「働く」とは?」について述べてきた。本人においては、仕事を続けることで社会とのつながりが維持され、誰かの役に立てているという実感は生きがいにもつながり、金銭的な報酬のみならず、精神的報酬の獲得にもつながり、サクセスフルエイジングの実現にも寄与する可能性がある。就労がフレイル対策や健康寿命の延伸につながるとすると、社会保障費の圧縮だけではなく、介護離職などによる経済損失の回避にも関わってくるため、高齢就労者が働き続けることの価値については多角的な視点での評価が必要であろう。
若い時に比べると身体機能は低下しているため、年齢にあった働き方をする必要があり、企業としても、高齢者が働きやすい環境づくりを行うこと(エイジズムの打破も含む)が必須となる。エイジズムの打破については、レイシズム、セクシズムをなくすのに有効であった方法を活かすことを示唆する論文(22)もある。ただし、高齢就労者自身もすべてをお膳立てしてもらえるなどと考えるのではなく、新しい環境に適応するための努力や前向きで柔軟な姿勢を持つことが求められる。つまりは企業と高齢就労者の共創が求められる。はじめから100点満点の就労環境ができる保障はないため、PDCAサイクルをまわしていくことも求められるであろう。高齢者の就業意欲と実際の就業形態におけるギャップに関する研究(23)からは、就業におけるマッチングの精度の向上の必要性も示唆される。
本人と家族、という観点でいうと就労前に十分に話し合いをしておいた方が良い。どのような働き方になるのか、家庭における家事、さらには介護などの役割をどのように分担するのかなどの合意形成ができていれば、本人の健康の維持だけではなく、夫婦間の距離も適度に保たれ円満な夫婦関係の維持にも寄与するであろう。
社会保障費の増加など、前例のない高齢社会に突入している日本において、健康寿命の延伸は一大テーマとなっている。先述した社会保障費だけではなく、経済の観点でも高齢労働者が精力的に働く環境づくりが進むと日本全体の生産性向上にもつながる可能性がある。また、世帯構成の多様化やIT技術の進化により希薄化する人と人とのつながりを取り戻すいいきっかけともなる。
経済発展は少子化につながり、結果的に高齢化への道をたどることとなる。まさに今ASEAN諸国がそのルートに乗っているわけであるが、高齢化する社会の理想の在り方を世界でもっとも早く実現する機会が訪れているのが日本であり、私も他人事ではなく自分事として、世界に誇れる高齢化社会の実現のため行動を起こしていく。
《参照》
老年心理学第1~6回資料
リフレクションシート第1~6回
1.総務省(2022年)『令和4年版 情報通信白書』「第2部 第1章 第2節 1(1)高齢者の就業・社会参加」
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/html/nd121110.html (最終閲覧:2025年7月6日)
2.総務省統計局(2024年)『統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-(統計トピックスNo.142)』
3.首相官邸「一億総活躍社会の実現に向けた政府の動き」2017.12.05
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/seifu_ugoki.html (最終閲覧:2025年7月6日)
4.内閣官房(2017年)『一億総活躍社会の実現に向けた政府の動き』首相官邸ホームページ
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/zenbun/pdf/1s1s_03.pdf (最終閲覧:2025年7月6日)
5.梅谷進康・石田易司・信達和典・松尾まどか・今井大輔・中野堅太・恩田泰輔(2017).高齢者の社会参加と生きがい―就労・ボランティア活動と生きがい要素に係る意識との関係―.聖学院大学総合研究所紀要,25(3),43-61.
6.Reichstadt et al., Am J Geriatr Psychiatry, (2010)「Older Adults’ Perspectives on Successful Aging: Qualitative Interviews」American Journal of Geriatric Psychiatry18,P567–575
7.東京新聞(2025年)「介護離職、年間10万人超 経済損失9兆円超の試算も」東京新聞デジタル
https://www.tokyo-np.co.jp/article/329787 (最終閲覧:2025年7月6日)
8.飯島勝矢(2020)『在宅時代の落とし穴 今日からできるフレイル対策』KADOKAWA.
9.経済産業省ヘルスケア産業課(2024年3月)『経済産業省における介護分野の取組について』。厚生労働省ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221559.pdf (最終閲覧:2025年7月6日)
10.西田裕紀子(2024年)「高齢期における知能の加齢変化」公益財団法人長寿科学振興財団ホームページ
https://www.tyojyu.or.jp/net/topics/tokushu/koureisha-shinri/shinri-chinouhenka.html (最終閲覧:2025年7月6日)
11.栗盛須雅子(2023年)「社会参加と健康長寿」公益財団法人長寿科学振興財団ホームページ
https://www.tyojyu.or.jp/net/topics/tokushu/kenkochoju-ikigai/shakaisankatokenkochoju.html (最終閲覧:2025年7月6日)
12.厚生労働省(2024年)『2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況』
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa23/dl/10.pdf (最終閲覧:2025年7月6日)
13.内閣府男女共同参画局(2020年)『男女共同参画白書 令和2年版 I-特-1図 男女別に見た家事・育児・介護時間と仕事等時間の推移(週全体平均)(年齢階級別,昭和51年→平成28年)』
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-00-01.html (最終閲覧:2025年7月6日)
14.厚生労働省(2025年)『65歳超雇用推進助成金について』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html (最終閲覧:2025年7月6日)
15.エスプール「プロフェッショナル人材バンク」
https://komon-haken.spool.co.jp/ (最終閲覧:2025年7月6日)
16.経団連(2024年)『高齢社員のさらなる活躍推進に向けて』
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/033_honbun.pdf (最終閲覧:2025年7月6日)
17.株式会社日本能率協会マネジメントセンター(2025年)「リバースメンタリングとは?導入方法や事例を徹底解説」
https://www.jmam.co.jp/hrm/column/0092-reverse-mentoring.html (最終閲覧:2025年7月6日)
18.内閣府(2024年)『令和6年版 高齢社会白書』
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/zenbun/pdf/1s1s_06.pdf (最終閲覧:2025年7月6日)
19.小池高史(2024年)「就業と健康長寿」公益財団法人長寿科学振興財団ホームページ
https://www.tyojyu.or.jp/net/topics/tokushu/shakaisanka-kenkochoju/shugyo-kenkojumyo.html (最終閲覧:2025年7月6日)
20.大和総研(2015年)「ASEAN諸国における高齢化の進展」
https://www.dir.co.jp/report/consulting/research_analysis/20151207_010396.html (最終閲覧:2025年7月6日)
21.田中耕太郎(2000).介護手当(金銭給付)の意義、実施状況およびその評価.海外社会保障研究,131,24-36.
22.小松, 秀雄. (2002). 現代社会におけるエイジズムとジェンダー. 女性学評論 = Women’s Studies Forum, 16, 23–42. 神戸女学院大学女性学インスティチュート編
23.浦川, 邦夫. (2013). 高齢者の就業意欲と実際の就業形態との格差 . 經濟學研究, 80(2–3), 53–67. 九州大学経済学研究院