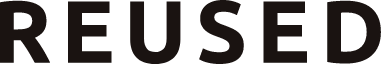GifTsというPJに2月から関わっています。
3月までの期間限定のPJとなり、学生と社会人がチームを組んで、
軽井沢の地域課題を解決するソリューションを提案する、そのようなものです。
私はヘルスケアというチームに入っており、学生4名社会人3名という構成となっています。
ショウワニアのPJで全国各地での展開を狙っているので、
軽井沢の地域課題に触れることもとても学びになります。
学生さんも様々なバックグラウンドをもっており、自身の学生時代と比べると
とても完成度の高い面々で、例えばプレゼン資料の作成ひとつをとってもクオリティが非常に高い、
優秀そのものですね、メンバーには現段階でもこども食堂に関わるメンバーも居て在り方も整っている、
各自の原体験などを基に課題の焦点の当て方として地域に住む高齢の方と子どもをどのようにつなぐか、
という形に決まりましたが、あとはそこにどのように軽井沢という個性を加えていくか、
興味深い企画アイデアがいくつも出ていますが、最終的には自分たちがそれを考えてワクワクするか、
そこがポイントになるでしょう、的なことをフィードバックさせていただいています、
学生は主に2年生中心なわけですが、彼彼女たちの将来に何らかのポジティブな及ぶと嬉しい限り
プロダクトアウト的な思考
サーキュラーエコノミーのシンポジウム的なものに参加をさせていただきました、
産総研さんの主催されているもので技術の話などを中心に各社が発表を行うというもの、
IRIEPがポスター展示を行うということもあり、専務理事たちと共に行ってまいりました、
登壇しておられる方にも質問をさせていただいたのですが、そのような場において気になる点、
ともすると、専門家が集まる場においては、消費者という存在が置き去りにされているということ、
ビジネスにおいて、プロダクトアウトかマーケットインか、と大きく2つのアプローチがあります。
例えば、デジタルパスポートに代表されるように商品のトレーサビリティを明らかにしましょう、
これはBtoBにおいては受け入れられやすいことだと思います、がToCと言われる消費者においてはどうでしょうか、
専門家はリユースアイテムのトレースがしっかりとしていることで買いやすくなるでしょう、と、
本当にそうでしょうか、個人的な考えにはなりますが、消費者がリユースに最も求めることは
「お値打ち価格」ではないかと。賢い消費、のような考え方もありますよね、
先程の2つのアプローチでいうと、プロダクトアウト的な発想にどうしても陥りがち、
そこで問わないといけないこととして、「自分が当事者になったと過程して心底そう思えるか」果たしてどうでしょうか、仮にある著名人が前所有者です、などということには一部のアイテムにおいてトレースの価値が生まれるかもしれませんが、大抵のものには生まれないのではないでしょうか、
少し話は変わりますが、危機管理という言葉や企業のコンプライアンスという言葉があります、
私の知人が大手メーカーで危機管理のプロとして仕事を行っているわけですが、彼は興味深いことを行っていて、「人が居るから危機管理が必要なのだ」と、つまりは理論的には安全でも人が予測不能な行動を取るゆえにイレギュラーが発生し、結果危機管理が必要になる、企業のコンプライアンスも然りで、コンプラが大事というのは誰しもが知っていることで、とはいえ、究極の場面になぜそのような選択肢を採用したのか、という選択を人がとってしまうために様々な問題が生じてしまうわけですね、
同じサーキュラーエコノミーでも少し視点を変えた話しをしてみます、
特に最近感じることではありますが、SDGs以降環境に関する話が盛り上がっています、脱炭素なる言葉もしかり、そこで主に論じられているのは「これから」つまりはまだ起きていない未来の話であることが多く、それはそれでとても大事なことです、

これまでをどうするか?の発想
しかし、同様に大事なのが「これまで」をどうするか、という議論でリユースというのはまさにそこにヒットするわけですが、サーキュラーエコノミーの文脈でもあまり語られることがないように感じます、
実際に隠れ資産66兆円などというデータも出ていますが、このマーケットはあらゆる産業と比較しても非常に大きいです、
また、シニアビジネス界隈の方々とも接点を定期的に持つようにしていますが、
これまでをどうするか、という点においてはキーとなるのがシニアビジネスでもあります、
環境という視点で考えると、実はサーキュラーエコノミーとシニアビジネス領域はとても近くにいる、
しかし、双方の場を行き来していても、双方の距離が非常に遠いということで、近接した場所にいるということ自体を考えている人もほぼ居ないでしょう、
デザイナーの原研哉さんがあるインタビュー動画でざっくりういうと、自分なりの解釈をすると自然なもの以外は残らない、的なことを述べておられました、何かを世の中に対して伝えようと考えた際に、「それは自然か」という問いを立てることも大事かもしれません、
行動経済学という学問がありますが、人という生き物をサイエンスしたうえで、例えばダークパターンのように陥れるようなことを行ったり、長期的に見るといわば不自然なものは徐々に淘汰されていくのではないかとも感じています
先般、デザインの領域でお仕事をしておられる方が、「めんどくささの先にしか良いものは生まれない」ということをおっしゃられておりました、まさにその通りで効率効率効率と効率が求められる世の中ではありますが、いかに「効果」を高めるか、そこにもフォーカスを当てていきたいところですね